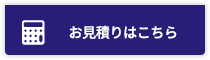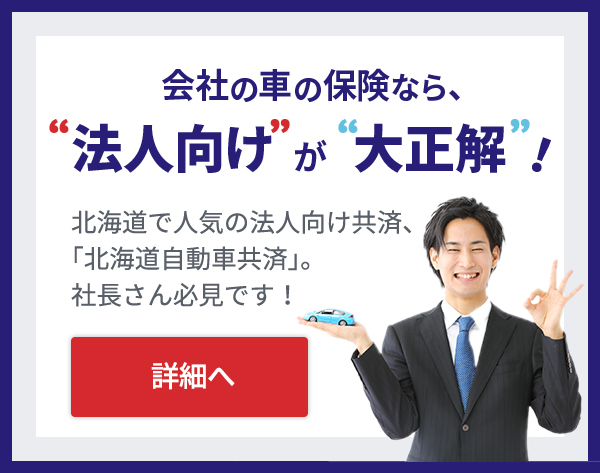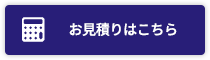個人契約でずっと無事故を続けてきた自動車保険・共済の等級(割引・割増)を法人契約に変更したとたんに、また最初の等級(割引・割増)から始まりますと言われたら、急に保険料(共済掛金)が上がり困ってしまいますよね。
そこで、おすすめなのが、法人自動車保険・共済の「等級の引き継ぎ」という方法です。
自動車保険(共済)の等級を引き継ぐことにより、基本的に保険料(共済掛金)が上がることを防ぐことができるからです。
このページでは、法人自動車保険(共済)の「等級の引き継ぎ」についての全てをお伝えします。
STEP1 等級制度を知ろう
自動車保険・共済の等級とは、1~20等級まであります。
最初は6等級もしくは7等級から始まります。1年間無事故ですと翌年1等級上げますよ、という仕組みになっています。尚、事故等で保険金支払いを受けると通常、等級は下がります。この等級(無事故割増引)は最大で20等級(63%割引)まで上がっていきます。もし、この等級(無事故割増引)を引き継がなければ、せっかく長年無事故ですすんだ等級(無事故割増引)がリセットされてしまいます。
現在は何等級になっていますか。
等級(無事故割増引)は、保険料(共済掛金)の計算に必要な確認事項のうちの1つです。
保険証券(共済証書)に記載されていますので確認しましょう。
※1~5等級(デメリット等級と呼ばれています)の場合は通常、リセットはされません。
STEP2 記名被保険・共済者は誰か知ろう
「記名被保険(共済)者」とは聞き慣れない言葉ですが「主に運転する者」をいいます。契約者と同一になっている場合が多いです。現在、どなたになっていますか。保険証券(共済証書)で確認しましょう。
自動車保険・共済の等級(無事故割増引)の引き継ぎに影響してくるのは、この記名被保険(共済)者になります。
※契約者及び車両所有者は、等級引き継ぎに影響しません。
STEP3 等級の引き継ぎができる間柄か知ろう
自動車保険(共済)の等級の引き継ぎはどんな間柄でもできるわけではありません。
等級の引き継ぎができるケース
- 個人事業主 ⇔ 個人事業主が代表の法人
- 個人事業主 ⇔ 同居の親族
- 同居の親族 ⇔ 同居の親族
等級の引き継ぎができないケース
- 個人事業主 ⇔ 個人事業主以外の人が代表の法人
- 個人事業主 ⇔ 別居の親族
- 個人事業主 ⇔ 従業員
- 個人事業主 ⇔ 他人
今回はどのケースに該当していますか。
STEP4 保険会社(共済組合)が変わったらどうなるか知ろう
ほとんどの保険会社(共済組合)は、等級を引き継いでくれますが、念の為、事前に保険会社(共済組合)へ問い合わせをし、確認するとよいでしょう。
まとめ
せっかく長い間積み上げてきた無事故割引を法人契約に変更しても引き継ぐには4つのステップが必須です。
- 等級制度を知る
- 記名被保険・共済者を知る
- 等級の引き継ぎができる間柄か知る
- 保険会社(共済組合)へ連絡する
せっかく頑張って長年無事故で育ててきた等級がリセットされて損をしない為にも等級を引き継ぐ法人自動車保険(共済)をぜひ知っておきましょう。